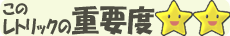サイト全部のトップ
サイト全部のトップ交差配語法 こうさはいごほう chiasmus
![『君が主で執事が俺で』1巻表紙(白猫参謀・皇ハマオ[著]、みなみそふと[原作]/角川書店 角川コミックス・エース)](http://www.fukirhetoric.com/image/jpg/kimiaru1.jpg)
- 『君が主で執事が俺で』 1
- 白猫参謀&皇ハマオ
- [原作]みなみそふと
交差配語法は、2つの似たことばを順序を逆にして繰り返すレトリックです。つまり、「AB-B’A’」という順番で、ことばを並べるレトリックです。
なので。
ちょっと長くなりますが、くわしく説明することにします。
「交差配語法」のつくりかた。
- あることば「A」と、それに似たことば「A’」を、用意します。
同じようにして、もう1つのことば「B」と、それに近いことば「B’」を準備します。
このようにしてできた、「A」「A’」「B」「B’」という4つのことばを、
「AB-B’A’」という順番にならべます。
このようにすると、類似のことばを順番を逆にしながら反復することになります。
とまあ。これが、「交差配語法」です。
しかし。
これでもまだ、かなり分かりにくいと思います。これでもやっぱり、抽象的な説明になっているからです。
なので。
《例文を見る》のほうで、「例文」といっしょに確認してみることをおすすめします。
 同じことばを反復するわけではないので、すこし不明瞭
同じことばを反復するわけではないので、すこし不明瞭
- 「交差配語法」では、2つの似た単語をくり返します。「 倒置反復法」のように、同じ単語を反復するわけではありません。そのため、少し鮮やかに欠けるレトリックになります。
 :不鮮明、ぼうっと、ぼんやり、朦朧、くもり、不明瞭、漠然
:不鮮明、ぼうっと、ぼんやり、朦朧、くもり、不明瞭、漠然
 使ったヒトは、みずからの主張を強く示そうとしている
使ったヒトは、みずからの主張を強く示そうとしている
- 「倒置反復法」には及びませんが。この「交差配語法」でも、「 倒置反復法」に似た効果を出すことができます。なので、この「倒置反復」を使ったヒトは、なにか主張をしていると考えられます。
 :主張、申し立てる、言い張る、打ち出す
:主張、申し立てる、言い張る、打ち出す
 対称のカタチをとるので、調和やバランスを感じる
対称のカタチをとるので、調和やバランスを感じる
- この「交差配語法」は、似た意味の単語を、鏡のように対称にして反復します。そのため、「 倒置反復法」にかなり近い美しさを出すことができます。
 :対称、つりあう、バランス、シンメトリー、調和、対比、相対する、対照、対置、対する、対照美、対応、引き合う
:対称、つりあう、バランス、シンメトリー、調和、対比、相対する、対照、対置、対する、対照美、対応、引き合う
 くり返しをするため、ことばを強めることになる
くり返しをするため、ことばを強めることになる
- このレトリックは、似たことばをくり返しています。言いかえれば、同じような単語が2回出てくるわけです。このことから、「交差配語法」を使うことで伝えたいメッセージを強調することができます。
 :強め合う、強める、強まる、盛り上げる
:強め合う、強める、強まる、盛り上げる
 ととのった、キレイな形をつくりだす
ととのった、キレイな形をつくりだす
- 似た言葉をくり返して、しかも順番を入れかえている。このことから、ととのった美しさのある文になります。
 :優美、風格、切れ味、美しい、きれい
:優美、風格、切れ味、美しい、きれい
 使い手に「才能」や「機知」があるイメージをあたえる
使い手に「才能」や「機知」があるイメージをあたえる
- このレトリックは、かなり技術的なものです。意識せずに使うということは、まずありません。そのため、使い手に「知性」などのイメージをもつことができます。
 :才気、才能、機知、知性、警句
:才気、才能、機知、知性、警句
 似たカタチをした同じ単語を、くり返す
似たカタチをした同じ単語を、くり返す
- このレトリックは、似た単語をくり返します。「 倒置反復法」では、まったく同じ単語を反復します。ですが、「交差配語法」では、意味の近い2つの単語をくり返します。
 順番を入れかえて反復する
順番を入れかえて反復する
- たとえば、さいしょに「AB]という順番で登場したばあい。次には必ず「B’A’」という順番で、あらわれることになります。まあこれは、日本語ではあまり問題になることはありません。
 「わざとらしさ」を感じることがある
「わざとらしさ」を感じることがある
- このレトリックは、かなり「わざとらしさ」を感じてしまうこともあります。つまり、ことばの受け手の印象に残るように、「わざわざ」使っていると感じとられることもあります。
 :わざとらしい、わざわざ、自発的
:わざとらしい、わざわざ、自発的
 単語の結びつきが異常になることがある
単語の結びつきが異常になることがある
- とくにヨーロッパのことばでは、語順のルールが厳しくなっています。ですので、ことばを倒置してしまうと、文法のルールに違反してしまうことがあります。これは、日本語ではあまり問題にはなりません。
 :不正、異常、異状
:不正、異常、異状
- とりあえず。
『君が主で執事が俺で』というフレーズが、典型的な「交差配語法」です。なので、この『君が主で執事が俺で』というヤツを、例文にしてみたいと思います。
この『君が主で執事が俺で』というのは、さいしょはゲームとして発売されたものです。ですが、アニメ化などのメディアコンプレックスによって、いろんな派生ジャンルに広がっています。コミックスも発売されているので、「ふき出しのレトリック」で紹介しても問題ないでしょう
で。
これがなぜ「交差配語法」なのかということを、《定義》で書いた説明に合わせて見ていくことにしましょう。そこで『君が主で執事が俺で』というフレーズを見ると。これは、上のならび方にしたがっていますなので、「交差配語法」だということができます。- あることば「君」と、それに似たことば「俺」を、用意します。
同じようにして、もう1つのことば「主」と、それに近いことば「執事」を、準備します。
このようにしてできた、「君」「俺」「主」「執事」という4つのことばを、
「君 主 - 執事 俺」という順番にならべます。
このようにすると、類似のことばを順番を逆にしながら反復することになります。
- あることば「君」と、それに似たことば「俺」を、用意します。
 「倒置反復法」と「交差配語法」との違い
「倒置反復法」と「交差配語法」との違い
- このページで紹介している「交差配語法」には、似たようなレトリックがあります。それは、「
倒置反復法」というものです。
問題となるのは、「 倒置反復法」というヤツ。これが、「交差配語法」とはどのように違うのかということです。つまり、「 倒置反復法」と「交差配語法」との線引きを、どのようにするか。そこに、ふれておきます。
おおまかに見たところ、大きく分けると説明のしかたは「4通り」に分かれているようです。ですので、その4つに分けて説明をしていきます。
なお、このサイトでは。下に書く から
から のうち、
のうち、 を採用しています。
を採用しています。
 このサイトでの説明に近いもの
このサイトでの説明に近いもの
- まず。
このサイトが採用したのは、次のような分けかたです。- 「 倒置反復法」のばあい、完全に同じことばが反復される。(AB-BA)
- 「交差配語法」のばあい、意味の近いことば・似たことばが反復される。(AB-B’A’)
というものです。
例をいくつか書いておくと。
倒置反復法:語順が「AB-BA」となっているもの(完全な言葉の反復)- ・「一は全、全は一」
- →『鋼の錬金術師』(荒川弘/スクウェア・エニックス ガンガンコミックス)の、5~6巻
- ※アニメでは第28話のタイトル
- ・「7人が1人 1人が7人」
- →『七人のナナ』(国広あずさ・今川泰宏/秋田書店 少年チャンピオン・コミックス)の、3巻177ページ
- ・「高校生といえばマック、マックといえば高校生だと」
- →『紳士同盟†(クロス)』(種村有菜/集英社 りぼんマスコットコミックス)の、5巻116ページ
交差配語法:語順が「AB-B’A’」となっているもの(不完全な言葉の反復)- ・「君が主で執事が俺で」(白猫参謀・皇ハマオ[著]、角川書店 角川コミックス・エース)
となります。
この説をとるメリット。それは、「倒置反復法」と「交差配語法」を間違いなく見わけることができる、ということです。「A」という単語と「B」という単語があって、それが「AB-BA」とならんでいれば「倒置反復法」になります。
それにたいして、この説のデメリット。それは、日本語のばあい「交差配語法」にあたる文をめったに見かけない、ということです。
私(サイト作成者)が、コミックスの中で「交差配語法」がにあたるとハッキリと言える例。それは、今のところ『君が主で執事が俺で』というタイトルしかありません。
なぜ、この「交差配語法」が数少ないのかというと。現実に使おうとしても、日本語ではインパクトの強い文章になりにくいからです。つまり、なにか「仕かけ」をしたフレーズだとは気がついてもらうことができにくい。そのため、そのまま気づかずに通り過ぎてしまう読み手=聞き手が多くなる。となれば、書き手=話し手としては、できればそういったことになるのは避けたい。結果として、「交差配語法」が使われることがあまりない。
とまあ、こんな事情が原因になっているのではないかと思います。
なお、この説をとっているものとしては、
『レトリック辞典』
があげられます。
 「交差配語法」と同じだとするもの
「交差配語法」と同じだとするもの
- これは、「倒置反復法」という用語と同じだとする考えかたです。
この説をとっているものとしては、『レトリックの本(別冊宝島 25)』(石井慎二[編]/JICC出版局)
をあげることができます。この本には、倒置反復(Antimetable)-順序を逆転して繰り返す。交錯配語法と同じ
と書かれています。そして、「交錯配列法」というのは、「交差配語法」と同じ意味の用語です。なので、明らかに「同じ」ものだということになります。
ですが。
この説では、同じ意味のレトリック用語が2つあることになります。そしてそれは、腑に落ちない感じがします。ですが、それ以外のことについては納得のいく説明だといえます。
 「交差配語法」と「倒置反復法」との区別を考えないもの
「交差配語法」と「倒置反復法」との区別を考えないもの
- これは。
「交差配語法」と「倒置反復法」との区別を、とりたてて問題としないというものです。- 『現代言語学辞典』(田中春美[編集主幹]/成美堂)
- 『現代英語学辞典』(石橋幸太郎[編集代表]/成美堂)
といった本では、関係なく2つのレトリック用語が掲載されています。たしかに、「交差配語法」の説明と「倒置反復法」の説明は、ほとんど同じモノです。けれども、この2つのレトリック用語の違いを書いたり比べたりといったことはしていません。そのため、なにか違う用語なのか、それとも同じような用語なのか。もしくは、まったく同じ意味なのか。それはハッキリしません。 - 『現代言語学辞典』(田中春美[編集主幹]/成美堂)
 「語句のくり返し」と「構成のくり返し」とで分ける
「語句のくり返し」と「構成のくり返し」とで分ける
- 「語句のくり返し」であるか、それとも「構成のくり返し」であるかによって、区別しようとする考えかたもあります。つまり、
- 「語句のくり返し」に対しては、「倒置反復法」とする
- 「構成のくり返し」に対しては、「交差配語法」とする
というものです。これにしたがうと、「単語それ自体」のくり返しについては、「倒置反復法」とすることになります。しかし、それ以外の「単語の意味・単語の形」といたもののくり返しについては、「交差配語法」という分類がされます
こういった説明については、『レトリック事典』
のほうに、ややくわしく書かれています。 - 「語句のくり返し」に対しては、「倒置反復法」とする
 対照法との関係
対照法との関係
- この「倒置反復法」をはじめとする、コントラストをつくるレトリックについては、「
対照法・対句」にまとめられています。
そちらもご参照ください。
 日本語には「交差配語法」が少ない
日本語には「交差配語法」が少ない
- 上のほうでも、ちょっと書きましたが。
この「交差配語法」というレトリック。日本語では、めったにお目にかかることがありません。
 なぜ日本語には、「交差配語法」が少ないのか
なぜ日本語には、「交差配語法」が少ないのか
- その理由をまとめると、つぎのようになります。
- 日本語では、「ことばのならべ方」をかなり自由にすることができる。
なので、もしも「ことばのならべ方」を入れかえても、あまり違和感がない。 - けれども、ふつう人間は、「ことばのならべ方」に違和感があるときに、
「なにかレトリックっぽい文章だ」ということを考えはじめる。 - ということは、
日本語では、ちょっと「ことばのならべ方」を入れかえたくらいでは、
「なにかレトリックっぽい文章だ」ということを考える人が少ない。 - なので、
「ことばのならべ方」がキーポイントとなる「交差配語法」は、
あまり効果的に使うことができない。 - といったわけで、日本語には「交差配語法」があまり使われない。
といったことになります。 - 日本語では、「ことばのならべ方」をかなり自由にすることができる。
 英語とかには「交差配語法」がある
英語とかには「交差配語法」がある
- なのですが、反対にいえば。
英語とかのヨーロッパのことばには、ちゃんと「交差配語法」が見つかるということでもあります。
たとえば。
このページで《例文》として使った、『君が主で執事が俺で』というタイトル。
もしこれを英語に直訳したばあい、You are the Master,the Servant is Me.といった文になります。
けれども困ったことに。
この英文は、明らかに英語の文法ルールに違反したものなのです。
たしかに、You are the Master,のほうは問題ありません。ですが、the Servant is Me.という文は、かなりの文法に逆らったフレーズです。この言いまわしでは、「倒置」された文だと受けとられることは確実です。もし中学校の英語のテストで書いてしまったら、不正解の文章になると思います。
なのですが。
それは、反対にいえば。ふつうとは違った「ヘンな形の文」だな、と感じるような文章だということになります。そして人は、「ヘンな形の文」を見せられた時に、その文章に注目します。で、そこに注目することによって「レトリックっぽさを強くかんじさせる」言いまわしだ、と感じることになります。
なので、英語の “the Servant is Me.” というフレーズは。
それが「ヘンな形の文」であるがために、「レトリックっぽさ」を感じさせることになるのです。
 その上で、もういちど日本語の文を考えてみる
その上で、もういちど日本語の文を考えてみる
- なのですが、反対にいえば。
日本語の、〈執事が俺で〉というフレーズ。これは必ずしも、日本語の文法に逆らったものだとはいえないということです。
たしかに、多く使われるのは〈俺が執事で〉というフレーズのほうだとは思います。ですが、〈執事が俺で〉という言いかたをすることもあります。「社長が俺で」「先生が俺で」「運転手が俺で」…というようなものも、日本語では「場合によっては使われることがある」言いまわしだと思います。
ですが、*The president is me. / *The teacher is me. / *The driver is me.といった文は、英語では「絶対にありえない」言いまわしです。
そして。
「絶対にありえない」からこそ。あえてこのような言いまわしを使うことが、「交差配語法」という名前をつけるほどのフレーズだということになるわけです。
まあ、そういったわけで。
日本語でハッキリ「交差配語法」だといえるようなフレーズは、かなり少ないということになります。

- 交差配語・交差配語法

- 交差配列・交差配列法・交錯配列・交錯配列法
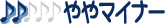
- 交錯語法・交差対句法・カイアズマス
 『レトリック辞典』(野内良三/国書刊行会)
『レトリック辞典』(野内良三/国書刊行会)
- 辞典としては、かなりの長く「倒置反復法」の説明が書いてあります。このページの「ネタ本」でもあります。
 『日本語の文体・レトリック辞典』(中村明/東京堂出版)
『日本語の文体・レトリック辞典』(中村明/東京堂出版)
- この辞典では。「交錯配列」とか「交差対句法」といった用語を、細かく分けて解説してあります。たとえば「交差対句法」という用語をつかうときは、「対句」がもっている警句っぽいかんじが強くなる、とか。そのあたりが気になるかたは、こちらを読んでみて下さい。