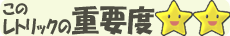サイト全部のトップ
サイト全部のトップ同綴同音異義 どうてつどうおんいぎ homonymy

- 一馬「あれ? 向こうに橋が
- あるんじゃない?」」
- 会長「おおっ 本当かい?」
- カルタ「帰れる」
- 看板―このはし
- わたるべからず―
- カルタ「これは…」
- 会長「このはし
- 渡るべからず…」
- 「真ん中を渡るやつか」
- 一馬「死ぬよ」
同綴同音異義は、2つの単語のつづりが同じで発音も同じだけども、表現する意味は別というレトリックです。つまり、つづりかたと音が全く同じでありながら、意味が異なることをいうものです。
 「同綴同音」のことばを、近くで使う
「同綴同音」のことばを、近くで使う
- 「同綴」というのは、つづりが同じということ。「同音」は、発音が同じこと。そして意図的に、この「同音」で「同綴」のことばを重ねたばあい、それが「同綴同音異義」となります。
 音が同じであったり、つづりが同じばあい、混乱しやすい
音が同じであったり、つづりが同じばあい、混乱しやすい
- 一般的にいって、「音が同じ」ことばや「つづりが同じ」のことばを並べることは、好ましくないとされています。どうしてかというと、「話しことば」では、同じ音のことばが何度も別々の意味で出てきたりすると、混乱してしまうからです。また、「書きことば」では、同じつづりのことばが何度も違った意味で出てきたりすると、読みにくい文になってしまいます。
ですので、ふつう「同音」のことばは重ならないようにするのがよいとされています。
- 画像は、『こいこい★生徒会』の2巻から。
主人公は、五光カルタ。彼女は、このたび生徒会のメンバーになった。
そこで、親睦会を兼ねた合宿をすることになる。
生徒会のグループは、ぜんぶで4人。
森の中にある合宿先に到着したあとで、露天風呂に向かう。合宿先から露天風呂まで、歩いて1時間以上もかかった。
問題は、その帰り道。合宿所に行くため、近道をする。これが大失敗で、道に迷ってしまう。そんな中、周りを見回してみる。
すると、ボロい橋を見つける。そしてそのワキには、看板が立っていた。いわく、[[dvsq「このはしわたるべからず」
この「はし」が、問題の「同綴同音異義」にあたります。
つづりは、ともに「同綴」(はし=はし)
発音は、ともに「同音」(ハシ=ハシ)
意味は、それぞれ違っているので「異義」(橋≒端)
といったわけで、「同綴同音異義」となるけです。なお、引用した画像にも書いてあるように。
一休さんは、「このはしを渡るべからず」とあったとき、「この橋」ではなく「この端」だと読みとりました。そして、端っこではなくまん中を歩いて、無事に渡りきりました。
ですが今回は、「この橋」を渡るのは危険です。「この端」を渡っても大変なことになります。なので、あえて両方の読み取りかたのできる看板を置くのは、あまり意味がなさそうです。
 「同綴同音異義」は避けられやすい
「同綴同音異義」は避けられやすい
- さいしょのほうでも少し書きましたが、「同綴同音異義」ということばがあるのは、とても不便です。なにせ、「読んだだけ」「聞いただけ」ではどちらの意味だか判断がつきにくいのだから、誤解がおきやすくなってしまいます。
そこで、ふつうは「どちらかのことばを変える」ことによって、「同綴同音」ではなくなるようにします。具体的にいえば、- 書きかたを変える →「同綴」でなくなる
- 読みかたを変える →「同音」でなくなる
たとえば。
日本語には、踊りをするという意味の「バレエ」と、相手のコートにボールを打ち込むゲーム(排球)という意味の「バレー」があります。
どうして同じような音を持っていることばなのに、あえて「バレエ」「バレー」と書きかたが違うのか。それは、同じにしてしまうと混乱するからです。わざと「書きかた」を変えることによって、「同綴」でなくなるようにしているのです。
また、どうして「バレエ」は「平板なアクセント」なのに、「バレー」は「最初にアクセントがある」のか。それも、同じにしてしまうと混乱するからです。わざと「読みかた」を変えることによって、「同音」でなくなるようにしているのです。(もしかしたら、英語での「バレエ」のアクセントが影響しているのかも知れないけれど。)
そういったわけで、そもそも「同綴同音異義」のことば自体が、とっても少ないのです。そのため、この「同綴同音異義」というレトリックを探すのは、かなり難易度が高いと思います。
 「同綴同音異義」と「異綴同音異義」との関係
「同綴同音異義」と「異綴同音異義」との関係
- この「同綴同音異義(homonymy)」と似たものに、「
同音異綴異義」というのがあります。
一般的にいって「同綴同音異義(homonymy)」と「 同音異綴異義」との違いは、「つづり方」が同じがどうかで区別します。つまり、- つづりが同じ=「同綴」のばあいには「同綴同音異義(homonymy)」
- つづりが違う=「異綴」のばあいには「 同音異綴異義」
 「同綴同音異義」に似たレトリック用語との関係
「同綴同音異義」に似たレトリック用語との関係
- この「同綴同音異義」と似たレトリック用語は、いろいろとあります。それを図で示すと、次のようになります。
○は含む、×は含まないの記号。発音 綴り字 意義 Homophone ─ ○ × × ┬ Homonym Homograph ─ ○ ○ × ┘ └ × ○ × ─ Heteronym
『現代英語学辞典』(石橋幸太郎[編集代表]/成美堂)から抜粋
上の図を見ただけでも、かなり混乱していることがわかります。
たとえば「Homograph」は、発音と綴り字が同じで。意義が異なるものをさす。けれども、発音と意義が違っていて、綴り字が同じもののことを言う場合もある。
といった感じで、うまくまとめることは、非常に困難です。
 「同綴」なっている単語どうしの、意味のつながり
「同綴」なっている単語どうしの、意味のつながり
- 「同綴同音異義」になっている、1つのペア。このペアあいだには、意味などで何らかのつながりがあるのでは…、と思いがちです。ですが、「同綴同音異義」をつくっている単語どうしは、たまたま同じ綴りで、しかも同じ発音だったというだけです。語源などに、つながりはありません。

- 同綴同尾異義
 『現代言語学20章—ことばの科学—』(ジョージ・ユール[著]、今井邦彦・中島平三[共訳]/大修館書店)
『現代言語学20章—ことばの科学—』(ジョージ・ユール[著]、今井邦彦・中島平三[共訳]/大修館書店)
- 「同綴同音異義」と「多義性」について、書かれています。また「同綴同音異義」についても、基本的な説明がされています。