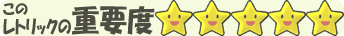サイト全部のトップ
サイト全部のトップ緩叙法(二重否定) かんじょほう(にじゅうひてい) litotes
![『涼宮ハルヒの憂鬱』3巻83ページ(谷川流[原作]・ツガノガク[漫画]/角川書店 角川コミックス・エース)](http://www.fukirhetoric.com/image/jpg/haruhi3-83.jpg)
- みくる「あ…あの どうでしょうか…?」
- キョン(悪かろうはずが
- ありません)
緩叙法(二重否定)は、手前に出てきた否定的な文を、さらに否定するものです。前に出てきた否定的なフレーズを、否定する。このことによって、かえって強調します。
 「否定的なコトバを否定する」ことによって、受け手に訴える
「否定的なコトバを否定する」ことによって、受け手に訴える
- 前に出てきた否定的なフレーズを、否定する。このことによって、かえって強調する。これが緩叙法(一重否定)です。
 :強い、強力、力強い、強み、強調、(受け手に)訴える、(意味を)強める、強化、増強、盛り上げる、盛りあがる
:強い、強力、力強い、強み、強調、(受け手に)訴える、(意味を)強める、強化、増強、盛り上げる、盛りあがる
 遠回しにすることによって、婉曲的・間接的な表現にする
遠回しにすることによって、婉曲的・間接的な表現にする
- 否定の意味を持ったことばを、さらに否定する。これは、遠回しにした表現だと言えます。ですので、間接的な表現をとりながら、実際には強めの表現になることもあります。
 :やわらげる、緩む、緩める、和らぐ、緩和、クッション、ほぐれる、なごむ、含みのある、含む、それとなく、暗に、こっそり、こっそりと、ぼかす、ぼける、ほかし、ぼやかす、ぼやける、くねらせる、くねくね、うねうね、婉曲語法
:やわらげる、緩む、緩める、和らぐ、緩和、クッション、ほぐれる、なごむ、含みのある、含む、それとなく、暗に、こっそり、こっそりと、ぼかす、ぼける、ほかし、ぼやかす、ぼやける、くねらせる、くねくね、うねうね、婉曲語法
 使い手が横柄で尊大だということをあらわす
使い手が横柄で尊大だということをあらわす
- 持って回ったコトバづかいをすることによって、緩叙法を使う。それが時として、えらぶっているという表現となることもあります。
 :高慢、尊大、傲慢、驕慢、傲然、傲岸、不遜、居丈高、高姿勢、高飛車、威圧的、高圧的、生意気、もったいぶる、思わせぶり
:高慢、尊大、傲慢、驕慢、傲然、傲岸、不遜、居丈高、高姿勢、高飛車、威圧的、高圧的、生意気、もったいぶる、思わせぶり
 「否定の否定」をする
「否定の否定」をする
- 緩叙法(二重否定)を使いたい。その時には、「否定されたことを、さらに否定する」という手順をふむことになります。その手順は、遠回しで婉曲な表現となります。緩叙法(一重否定)には、「強める」効果と「遠回しにする」効果の2つがあります。ですが、「否定を否定する」という手順には変わりありません。
 :遠回し、婉曲、回りくどい、持って回った、ねちねち、くだくだ、間接性、遠い、縁遠い、迂回性、迂回
:遠回し、婉曲、回りくどい、持って回った、ねちねち、くだくだ、間接性、遠い、縁遠い、迂回性、迂回
 二重否定は、受け手に負担をかける
二重否定は、受け手に負担をかける
- 上にも書いたように緩叙法(二重否定)では、語や文がからみ合って登場します。そのため受け手(読み手・聞い手)に、負担をかけることになります。ですので、それほど多く使うことは見合わせておいたほうが無難です。
- 引用は、『涼宮ハルヒの憂鬱』3巻から。
ここでの登場人物は、2人。みくると、主人公のキョン。
2人は、SOS団(という同好会)に、無理矢理に入団させられていた。
(なお、SOS団とはなにか、については省いておきます。涼宮ハルヒといった存在あるかも、本のタイトルにキッチリ『涼宮ハルヒ』と書いてありますが、省略します)
ある日のこと。キョンはみくるから「今度の日曜日… 一緒に買い物生きませんか…?」と誘われる。そんなわけでキョンは、みくると日曜日に集合することになった。
みくるのお目当ては、ブティック。試着する、みくる。そして、いちばん上に書いた引用です。
キョンの感想。悪かろうはずがとのこと。
ありません
この文をよく見てみると、悪かろうはずがとなります。
ありません
まずはじめに、「悪い」ということば出てくる。これは、いうまでもなく「否定的なことを示す単語」です。この単語をさらに、「ありません」ということばによって、否定します。この結果、「良い」ということが強調されることになります。
![『さくら荘のペットな彼女』1巻65~66ページ([原作]鴨志田一<br>・[作画]草野ほうき・[キャラクターデザイン]溝口ケージ(アスキー・メディアワークス 電撃コミックス)](http://www.fukirhetoric.com/image/jpg/petnakanojo1-18.jpg)
- 空太「あんたは
- ほんとに聖職者か!?
- 聖職者としての[li]]自覚を持て!!」
- 千石先生「聖職者の自覚?
- そんなの
- 父親の睾丸の中に
- 忘れてきたわよ」
- 空太(うわぁ…)
- 「女の人が睾丸って言うの
- はじめて聞きました」
- 「さすが三十路は
- 違いますね」
- 千石先生(ピキッ)
- 「誰が三十路ですって~!?
- 私はまだ
- 29歳と15か月よ!!」
次の例は、『さくら荘のペットな彼女』1巻から。
これは、学生寮の「さくら荘」をめぐってのお話。
主人公の空太(そらた)は、「さくら荘」の住人。そして、いま「さくら荘」に来ているのが千石先生。美術教師。
ここで千石先生は空太に、とてつもなく困った相談をもちかけてくる。いや、「相談」ではない。「渡す物がある」と、持ってきた写真を空太に見せる。そして、写真の人物とは「駅に6時に駅で待ち合わせをしているので、迎えに行って」と言われる。これは、どちらかというと「命令」に近いと思う。
そして、この「命令」を受ける受けないということで言いあいになっている。
売り言葉に買い言葉で、空太は「(先生も)三十路だ」というセリフを吐く。
たしかに千石先生も、人間なので年をとる。だけれども、29歳になったあとで誕生日を迎えると、30歳になるはずです。
ところが千石先生は、自分はまだ「29歳と15か月」だと主張している。そして、そのことを理由に「まだ三十路ではない」と言っています。
ここにある誰が三十路ですって~!?というところが、「緩叙法(一重否定)」になります。
この文を、分かりやすくしてみると、三十路であるはずがありませんとなります。- まずはじめに、「三十路」ということば出てくる。これは、会話の成りゆきから考えて、「否定的なことを示す単語」だといえます。この単語をさらに、「ありません」ということばによって、否定します。この結果、「30歳にはなっていない」という(無理のある)主張が強調されることになります。
- ですので、「緩叙法(一重否定)」になります。
 緩叙法の分類
緩叙法の分類
- 緩叙法とは、弱めの表現を使うことによって、逆に強める意味をもともののことをいいます。ですので、「ひと目見たばあいは、意味をやわらげる」。でも「実際には、ことばを強める効果を持つ」という2つの条件をみたしているのが、緩叙法です。
で。具体的に「緩叙法」に含まれるパターンがあるか。それをあらわしたのが、下の図となります。
この図を見ることによって、「緩叙法」全体が見えてくるのではないかと思います。┌
┤
│
└否定を用いる ┬
└一重否定(悲しくはない→うれしい) 緩叙法 二重否定(うれしくないわけではない→うれしい) ┌
┼
└選択(好意を持っています) 否定を用いない 付加(少し酔っぱらった) 指小辞(小鳥の「こ」) 『レトリックの知—意味のアルケオロジーを求めて—』(瀬戸賢一/新曜社)より
このページのタイトルは「緩叙法(二重否定)」です。なので、上に表では、一番上にある「否定を用いる」のなかの「二重否定」にあたります。
 「二重否定」は「緩叙法」に含まれるか
「二重否定」は「緩叙法」に含まれるか
- すぐ上の項目にある図。これだと、二重否定は問題なく「緩叙法(二重否定)」にあたりそうです。しかし、ここには疑問だとする意見もあります。
その表を作った瀬戸賢一氏が[[[svsq- これ(二重否定)を緩叙法に含めて考えてよいかどうかは、微妙なところであろう。
- ——『レトリックの知—意味のアルケオロジーを求めて—』(瀬戸賢一/新曜社)
ですが、
- (二重否定は)緩叙法の一形態。
- ——『日本語レトリックの体系—文体のなかにある表現技法のひろがり—』(中村明/岩波書店)
- 二重否定もここ(緩叙法)にいれてよい。
- ——『レトリック辞典』(野内良三/国書刊行会)

- 緩叙法(二重否定)

- 曲言法
 『レトリック辞典』(野内良三/国書刊行会)
『レトリック辞典』(野内良三/国書刊行会)
- ある程度の長さをもった説明が、されている本としてあげておきます。ほかに、同じ者の本として『日本語修辞辞典』(野内良三/国書刊行会)などもあります。
 『大学生のためのレトリック入門』(速水博司/蒼丘書林)
『大学生のためのレトリック入門』(速水博司/蒼丘書林)
- とりあえず、無難な本。とりわけ目をひく内容ではない。でも、基本となることがらを、ていねいにまとめてあります。