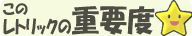![『半分の月がのぼる空』1巻144〜145ページ([原作]橋本紡、[作画]B.たろう/メディアワークス 電撃コミックス)](http://www.fukirhetoric.com/image/jpg/hantsuki1-144to145.jpg)
- ——ある日 里香が
- ポツリと言った
- ことがある
- 死は隣人なのだと
- 里香「わかるのよ
- そばにいるのが
- 手を伸ばしたら
- わぶん触れるわ
- それで わたしを
- どこかげ連れて
- いっちゃうの」
- ——(だから僕は願う
- 里香を
- 連れていかないで
- ください…)
-『半分の月がのぼる空』1巻144〜145ページ([原作]橋本紡、[作画]B.たろう/メディアワークス 電撃コミックス)祈願法は、なにかに願うことです。願いをする対象となるのは、だいたい神々です。
 大きな力を持った神などに、自分のおもうことを願う
大きな力を持った神などに、自分のおもうことを願う
- 「祈願法」は、なにかの助力を求めて、祈願したり訴えたりするものです。なので、自分の力ではどうすることもできないという状況であることを知らせる効果があります。
 :祈願、祈る、こいねがう、切望する、希求する、祈祷する
:祈願、祈る、こいねがう、切望する、希求する、祈祷する
 神とかに祈る
神とかに祈る
- 「祈願法」で、なにかを願うことになる相手。それは、ほとんどのばあい「神」です。この「祈願法」というレトリック用語が生まれた古代ギリシャ・ローマは、「多神教」でした。なので「祈願法」というレトリック用語は、さまざまな神々に祈ることを意味しました。
 …っていうか、こんなの「祈願法」というレトリック用語をつくらなくても。
…っていうか、こんなの「祈願法」というレトリック用語をつくらなくても。
- レトリック学者は、分類がとても大好きです。なので、「祈る」なんていう、どうでもいいことにも名前をつけてしまいました。実際には、そんな取りたててネーミングをするほどのものではありません。
- 引用は、『半分の月がのぼりる空』1巻からです。
主人公は、裕一。
裕一は、2〜3ヶ月の入院をすることになってしまった。病名は、急性肝炎。
そして。その病院で裕一は、一人の女の子と出あう。名前は、里香。年齢は、裕一とおなじ17歳。
裕一は、そんな里香と病院で知りあって、だんだん仲よくなっていった。だんだんと交流をふかめていくにつれて、里香のかかえている病気を知ることになっていく。
里香は、長いあいだの入院生活をおくっていた。というのは、心臓の弁膜がちゃんと動かないという病気をかかえていたから。そして。もし手術をしたばあいにも、亡くなってしまう確率のほうが大きい。それを知っている美香は、手術をためらっていた。
そういった、里香の病状を知るにつれて。里香は裕一に、あることを話しだした。そのことに対する裕一の思い。その思いがモノローグとなって、かたられている。それが、引用のシーンです。たしかに裕一は、祈っています。なので、「祈願法」といえます。こんなことについても、いちいちレトリック用語として名前をつける必要があるのか、ということには疑問がありますが。たしかに、「祈願法」です。
しかし。
裕一は、だれに祈っているのでしょうか。キリスト教の「神」なのか、仏教の「仏」なのか。それは、ちょっと分かりません。
そういえば、『半分の月がのぼる空』という作品の舞台は、伊勢です。なので、内宮にまつられている「天照大御神」なのかもしれません。もしくは、外宮にまつられている「豊受大御神」だったりするのかもしれません。
ですが、おそらく。
裕一は、そういった具体的な「神」や「仏」に願ったのではない。そう考えるのが、自然だと思います。だって日本人は、なにか1つの宗教を信じているヒトは少ないから。正月には、神社にいって参拝する。お盆には、お寺で墓参りをする。クリスマスにはキリストの誕生を祝う。——これが、ごくふつうの日本人だから。

 「祈願法」に近いレトリック
「祈願法」に近いレトリック
- このページで取りあげている、「祈願法」というレトリック。これには近いレトリックが、いくつかあります。なので、そのあたりを紹介しておくことにします。
- 宣誓・誓言
- (oaths)
- 神聖なものに誓う、というカタチをとるもの。ただし「誓う」という言葉は使ってはいるものの、実際には、その誓ったことばを強調するというニュアンスが与えられる程度。(*1)
- 宣言
- (swearing)
- もともとは、「神に誓う」という本来の目的があった。だけれども時代とともに、「みだりに神の名を口にすることになる。なので、神聖をけがす言葉づかいだ」という意味を持った。このため「宣言」という単語が、使った相手を非難する言葉を示すことになった。さらに、現代では「悪口を言うこと」「ののしること」ということも表すようになった。(*2)
- 願望
- (optation)
- これは、自分が望んでいるモノゴトを、感嘆を使って表現すること。願望する相手が「神や仏」に限らないというところに、ほかのものと違いがある。(*3)
- 祈願・懇願・嘆願
- (obsecration)
- 苦しいときに、神などの神聖なものに祈ること。日本人が正月に「神社仏閣」に行って(心の中で)祈るということ。それは、このレトリック用語がピッタリすると思う。(*4)
「祈り」のパターンを、4つに分けてみたのですが。こんなに、いろいろと分類することに意味があるのかはナゾです。
- 注(*1)『日本語の文体・レトリック辞典』、『日本語レトリックの体系』、『レトリックの本(別冊宝島 25)』(石井慎二[編]/JICC出版局) 』、ほか
- (*2)『現代英語学辞典』(石橋幸太郎[編集代表]、勇康雄・宇賀治正朋・勝又永朗・鳥居次好・山川喜久男・渡辺藤一[編集]/成美堂)、ほか
- (*3)『レトリック事典』、ほか
- (*4)『文学修辞学—文学作品のレトリック分析—』(H.ラウスベルク[著]、萬澤正美[訳]/東京都立大学出版会)、『レトリック事典』、ほか
 サイト全部のトップ
サイト全部のトップ![『半分の月がのぼる空』1巻144〜145ページ([原作]橋本紡、[作画]B.たろう/メディアワークス 電撃コミックス)](http://www.fukirhetoric.com/image/jpg/hantsuki1-144to145.jpg)
 大きな力を持った神などに、自分のおもうことを願う
大きな力を持った神などに、自分のおもうことを願う :祈願、祈る、こいねがう、切望する、希求する、祈祷する
:祈願、祈る、こいねがう、切望する、希求する、祈祷する 神とかに祈る
神とかに祈る …っていうか、こんなの「祈願法」というレトリック用語をつくらなくても。
…っていうか、こんなの「祈願法」というレトリック用語をつくらなくても。 「祈願法」に近いレトリック
「祈願法」に近いレトリック

 『レトリック事典』(佐藤信夫[企画・構成]、佐々木健一[監修]、佐藤信夫・佐々木健一・松尾大[執筆]/大修館書店)
『レトリック事典』(佐藤信夫[企画・構成]、佐々木健一[監修]、佐藤信夫・佐々木健一・松尾大[執筆]/大修館書店)