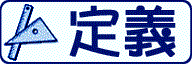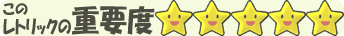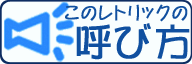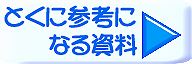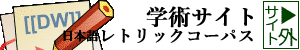サイト全部のトップ
サイト全部のトップ声喩・オノマトペ せいゆ・おのまとぺ 英語:onomatopoeia、フランス語onomatopée
![『撲殺天使ドクロちゃん』1巻8ページ([原作]おかゆまさき・[作画]桜瀬みつな/メディアワークス 電撃コミックス)](http://www.fukirhetoric.com/image/jpg/dokurochan1-8.jpg)
突然、机の引き出しから飛び出してきた女のコ。
その娘の名前は、撲殺天使ドクロちゃん。
彼女は、出会った瞬間に僕を撲殺。
撲殺したと思ったら、
ぴぴるぴるぴるぴぴるぴ〜♪
謎の擬音と共に、はい元通り。
彼女って、いったい何!?
――これは、僕とドクロちゃんの
愛と涙の血みどろ物語。
-『撲殺天使ドクロちゃん』1巻8ページ([原作]おかゆまさき・[作画]桜瀬みつな/メディアワークス 電撃コミックス)
 イメージを直接伝えることよって、印象を深くする
イメージを直接伝えることよって、印象を深くする
- この「
擬音語」や「
擬態語」といった「声喩・オノマトペ」を使うと、イメージを直接に伝えることができます。なので、相手に強く印象づけたい場合などに使うと効果的です。
たとえば、広告で宣伝文句として「 擬音語」や「 擬態語」をいれると、効果的になります。それは、受け手に強い印象を与えることができるので、広告の威力がおおきくなるからです。
 :イメージ、概念、観念、理念、心象、表象、印象、焼きつける
:イメージ、概念、観念、理念、心象、表象、印象、焼きつける
 感覚的に伝えられる部分で、「声喩・オノマトペ」を使う
感覚的に伝えられる部分で、「声喩・オノマトペ」を使う
- 伝えたいモノゴトのうちには、感覚的な音やイメージをもっていることがあります。このようなばあいには「声喩・オノマトペ」を使うことで、より感覚的に伝えることができます。
 :感覚的、悟る、感じ
:感覚的、悟る、感じ
 「声喩・オノマトペ」に含まれる、2つの分類
「声喩・オノマトペ」に含まれる、2つの分類
 正式な文章では、使ってはいけない
正式な文章では、使ってはいけない
- この「声喩・オノマトペ」は、話し言葉などといった「軽い」コトバのなかで使われます。ですので、「レポート」や「報告書」などといった文章には基本的には使わないほうがいいでしょう。
 ありきたりな「オノマトペ」を使ってはいけない
ありきたりな「オノマトペ」を使ってはいけない
- たとえば、小説を書く。そのときには必ずしも、「声喩・オノマトペ」を使うのが悪いとは限りません。ですが、ありきたりで陳腐な「声喩・オノマトペ」は、使ってはいけないものだといえます。「声喩・オノマトペ」が使われるとき、意外性を持っていることが大切なのです。
- 例文は、『撲殺天使ドクロちゃん』1巻。
引用したのは、表紙をめくって最初にでてくるページです。つまり、ここに書かれているのは「設定」というか「概略」そのものです。
といったわけで。どんなコミックスかというのは、読んでみたとおりです。
ちょっとフシギな設定ですが「ドクロちゃん」は、すぐに相手を撲殺します。そのために「エスカリボルグ」というヤツを標準装備しています。イラストの左手の手元に持っている金棒みたいなのが、それです。
で、撲殺する。
しかしながら、さすがは「天使」。この撲殺してしまった相手を、もとどおりにする能力まで持ち合わせている。
もとどおりにする、そのためには。ぴぴるぴるぴるぴぴるぴ〜♪という、「謎の擬音」を口ずさむ。
「擬音」
——そう。たしかに、ここには「擬音」と書いてある。じゃあ、これが「 擬音語」なのかというと…。かなり、あやしい。
なぜなら。
「 擬音語」と呼ぶためには。なにか「もとになる音」があって、それを「マネる」という必要がある。だとすると、「ドクロちゃん」は、いったい「何の音」をマネているのか。つまり、そもそも「もとになる音」というものが、いまいち分からない。
というわけで。
ここには「擬音」と書いてあるけれども。「ぴぴるぴる(略)♪」は、じつは厳密な意味での「擬音」ではない。そのように、私(サイト作成者)は考えております。
ただ。べつに、「ちゃんとキッチリと言葉を使い分けろよ!」と言いたいのではありません。『広辞苑』の中でもなければ、大学の教壇でもない。そんな場所で、四角四面な言葉づかいは求められてはいないはずだから。
あと。「擬音じゃないなら、なんなんだ!?」ということについては。このページの、ず〜〜〜〜っと最後のほうにある《余談》のところに書いてみました。
 日本語には「声喩・オノマトペ」が多い
日本語には「声喩・オノマトペ」が多い
- よく知られているように。日本語には、多くの「声喩・オノマトペ」があります。日本語には「
擬音語」だとか「
擬態語」だとかが、たくさんあるわけです。
これは、よく指摘されていることです。なので、みなさんご存じのことかと思います。
たとえば井上ひさし氏は『自家製文章読本(新潮文庫 い−14−19)』(井上ひさし/新潮社)の中で、「歩く」という動詞に関する「声喩・オノマトペ」として次のようなものをあげています。たとえば「歩く」という動詞がある。単独では弱いとみれば、われわれは「連れ歩く」「跳ね歩く」「捜し歩く」「買い歩く」「騒ぎ歩く」「出歩く」「流れ歩く」「渡り歩く」「彷裡(さまよい)歩く」というように、そのときの意味に合せて「歩く」に助太刀をつかわして強化する。がしかし「歩く」の内容をより具体的にし、できれば聴き手の感覚に直(じ)接(か)に訴えたいと思うときは、いそいそ、うろうろ、おずおず、ぐんぐん、こそこそ、ざくざく、しゃなりしゃなり、しおしお、すごすご、すたすた、すたこら、ずんずん、ずしんずしん、せかせか、ぞろぞろ、たよたよ、だらだら、ちまちま、ちょこちょこ、ずかずか、つかつか、てくてく、どかどか、のっしのっし、どすんどすん、どたどた、どやどや、なよなよ、のこのこ、のそのそ、のろのろ、ぱたぱた、ひょろひょろ、ふらふら、ぶらぶら、へろへろ、まごまご、もそもそ、よちよち、よたよた、よぼよぼ、よろよろ、わらわら……などのなかから、最もぴったり来る擬音・擬態語を選んで、「歩く」を補強するのである。と、43例ほどあげています。
このこと1つから見ても、日本語は「声喩・オノマトペ」をたくさん持っているということがわかります。
 マンガの「声喩・オノマトペ」
マンガの「声喩・オノマトペ」
- これもまた、よく知られているように。マンガには、多くの「声喩・オノマトペ」があります。つまり、マンガは日本語の中でも特に「
擬音語」もしくは「
擬態語」といったものが、たくさんみられるわけです。
結果として、「ふき出しのレトリック」というサイトをつくる私(サイト運営者)としては、ありがたいレトリックです。なにせ、例を探し出すのに事かくことのないのだから。
 「声喩・オノマトペ」の表記
「声喩・オノマトペ」の表記
- 『文章の技—書きたい人への77のヒント—』(中村明/筑摩書房)によれば、としています。
そしてこのことは、コミックスであっても当てはまると思われます。実際に数えてみて、くらべてみたわけではありません。ですが、私(サイト運営者)の感覚からすると、上に書いた法則がいちおう当てはまっています。
ただし。「 擬態語」をカタカナにする場合が、コミックスでは少し多いような気がします。
どうもこの、「 擬音語」はカタカナで「 擬態語」をひらがな、というのは。国語審議会の『国語問題要領』(1950)というヤツが、ルーツのようです。
 「擬音語」なのか「擬態語」なのかハッキリしないもの
「擬音語」なのか「擬態語」なのかハッキリしないもの
- と、書いてきたのですが。
実は、「 擬音語」と「 擬態語」とは、ハッキリと区別できないものもあります。
いちおう『大辞林』(三省堂)によると、とされています。しかし、「 擬音語」であるか「 擬態語」であるかがハッキリしない、あやふやなものが残ってしまうのが実情です。
『現代擬音語擬態語用法辞典』(飛田良文・浅田秀子[共著]/東京堂出版)から例を1つあげてみると、「ベーコンをかりかりに焼く」の「かりかり」というのは、どちらでしょうか。
どちらかというと「 擬音語」に見えます。食べるときには、そんな音が出そうにも思えます。ですが「かりかり」は、十分に火が通って焼き上がっている様子をあらわす「 擬態語」だと考えることもできます。このように、「 擬音語」なのか「 擬態語」なのかが判別しにくいものも、多くあります。
なお同書では、「かりかりに焼く」の「かりかり」は「 擬音語」でかつ「 擬態語」どちらかに区別することはできないとしています。
この「かりかり」のように、「 擬音語」と「 擬態語」とを完全に区分けすることはできません。また、区別することによって特別な意味があるとも思えません。
ですが一般に、「声喩・オノマトペ」には「 擬音語」と「 擬態語」の2タイプがある、ととらえるのが普通のようです。なので、「 擬音語」と「 擬態語」の2種類のページを作ることにします。
 「声喩・オノマトペ」は辞書に載りにくい
「声喩・オノマトペ」は辞書に載りにくい
- 「声喩・オノマトペ」のうちで辞書や辞典に載っているものは、少ししかありません。この「
擬音語」や「
擬態語」といったものは、あまり辞典や辞書に書かれていないのです。つまり、ある「声喩・オノマトペ」を辞書でひいてみても、掲載されていないということが多くあります。
この理由としては、次のようなものが考えられます。このような事情があると思われます。- 「声喩(オノマトペ)」は、世代交代が早い。つまり、すぐに「新しい」ものが登場する代わりに、「古い」ものは使われなくなるということが多い。そのため、辞書に載せにくい。
- 「声喩(オノマトペ)」は、新語が多い。つまり、新しくユニークな「声喩・オノマトペ」が次々と作られる。そのため、辞書に掲載するようになるまでに時間がかかる(そのため、「
新造語法」とも関連する)。
- 「声喩(オノマトペ)」は、方言が多い。つまり、各地方によって色々な「声喩・オノマトペ」がある。そのため、辞書に載せるような「標準語」を見つけられない。
- 「声喩(オノマトペ)」は、世代交代が早い。つまり、すぐに「新しい」ものが登場する代わりに、「古い」ものは使われなくなるということが多い。そのため、辞書に載せにくい。
 「声喩・オノマトペ」のかたち
「声喩・オノマトペ」のかたち
- この「
擬音語」や「
擬態語」で、いちばん数が多いのは、「ABAB」とくり返すものです。「フワフワ」「べたべた」「キャンキャン」など、例をあげるときりがありません。
そしてこのことは、現代に限ったことではありません。奈良・平安の時代から、「ABAB」とくり返す「 擬音語」や「 擬態語」が、「 擬音語」や「 擬態語」が、時代を問わずに多数を占めています。
また、奈良・平安時代の「 擬音語」や「 擬態語」は、現代にもたくさん受け継がれています。たとえば『今昔物語集』には「カラカラ」「コソコソ」「キラキラ」といってような、現代にも使われているものが登場します。
以上の分析は、『犬は「びよ」と鳴いていた—日本語は擬音語・擬態語が面白い—(光文社新書056)』(山口仲美/光文社)を参考にしました。
 「声喩・オノマトペ」のアクセント
「声喩・オノマトペ」のアクセント
- 「声喩・オノマトペ」のアクセントについて。
- 「
擬音語」や「
擬態語」を発音するときのアクセントは、特定のものに決まっているとのことです。
具体的には、- 「と」及び動詞に続く場合—「頭高型」
(「プンプン」「ぽかぽか」などで、「●○○○」というアクセントになる) - 「っと」に続く場合—促音の前まで高い
(「ふらふらっと」「ピカピカっと」などで、「○●●●○○」というアクセントになる) - 「だ・に・の」に続く場合—「平板型」
(「ふらふらになる」「ボロボロになる」などで、「○○○○」というアクセントになる)
ただしこれは、東京方言にみられる特徴です。他の地域では、この原則からはずれていることもあります。
これについては、『擬音語・擬態語の読本』(尚学図書[編]/小学館)を参考にしました。 - 「と」及び動詞に続く場合—「頭高型」
 「擬声語」とか「擬情語」とか
「擬声語」とか「擬情語」とか
- 「擬声語」とか「擬情語」ということばもあります。もっと細かく「声喩・オノマトペ」を分類しようとすれば、「擬声語」「擬情語」を独立させることもできます。
しかし、このサイトでは「 擬音語」と「 擬態語」の2種類の分類で書いていくことにします。
 「声喩・オノマトペ」は嫌われているのか
「声喩・オノマトペ」は嫌われているのか
このことについて。『思ったことを思い通りに書く技術(PLAY BOOKS)』(外山滋比古/青春出版社)によると、
こういう作法のようなもののよってきたるところの源はどうも森鴎外にあるらしい。
と、説明されています。同書にも書かれていることですが、「声喩・オノマトペ」を使うのがピッタリするときには、あえて使うのを避ける必要はないと思います。
もっとも、私が思うには。
たしかに。報告書や論文の中では、ふつう「声喩・オノマトペ」を使ったりすることはありません。厳格な文章を書くときには、「声喩・オノマトペ」を使わないように配慮するのが普通だと思います。
でも、そういった堅苦しい文章ではなく、もっと一般的な文章。宣伝文でもいいし、小説でもいい。もちろんマンガでもいい。そういった、日常に読むような文章で「声喩・オノマトペ」を使うこと。それを攻撃することは、間違っていると思います。「声喩・オノマトペ」には、他の表現では伝えられない良さがあるのだから。
 日本語よりも「擬態語」が多い言語
日本語よりも「擬態語」が多い言語
- 日本語よりも多くの「
擬態語」が用意されている言語は、おそらく朝鮮語だけです。
ちなみに朝鮮語では。
もともと副詞のはたらきをする「 擬音語」や「 擬態語」に接尾辞をプラスすることで、形容詞とか動詞として扱うことができるようになる。そのため、日本語よりも多種の大変な数の「 擬音語」や「 擬態語」ができる。ということらしいです。
なお。これ以上にくわしいことについては、『擬音語・擬態語の読本』(尚学図書[編]/小学館) を読んでみてください。
 「オノマトペ」という単語の語源
「オノマトペ」という単語の語源
- 「オノマトペ」という単語は、どこの言語から日本語に取りいれたものなのか。つまり、「オノマトペ」という単語の輸入元は、どこのことばなのか。
これは。「フランス語」から輸入されたものだということになっているみたいです。その、いちばん大きな理由は、「発音のしかたがフランス語っぽい」からというものです。
つまり、となる。それに対して、- もしも英語の“onomatopoeia”の発音を、そのまま写しとったのならば「オノマトピーア」。
- もしもギリシャ語の“onomatopoiia”の発音を、そのまま写しとったのなら「オノマトポイイア」。
になる。といったことを考えると、フランス語の“onomatopée”が日本に取りいれられたのだといえるのです。- フランス語の“onomatopée”の発音を、そのまま写しとると「オノマトペ」。
ではなぜ、わざわざフランス語の“onomatopée”が選ばれたのか。たいていのレトリック用語は、ラテン語とかギリシャ語とか、たまに英語だったりする。なのに、なぜ「オノマトペ」に限ってフランス語なのか。
これについて『日本語はおもしろい (岩波新書 373)』(柴田武/岩波書店)は、英語からのオノマトピーア、オノマトペア(onimatopoeia)より短かく、日本語になじませやすいということもあって、オノマトペ(onomatopée)というフランス語の形を採る。としています。
 onomatopéeという単語の意味
onomatopéeという単語の意味
 “onomatopée”を「擬態語」と翻訳していいか?
“onomatopée”を「擬態語」と翻訳していいか?
- 最後に。
いままで、いろいろ書いたわけですが。
じつは。“onomatopée”というフランス語は、ふつう「 擬音語」だけを意味するのです。つまり、「 擬態語」のことをふつうフランス語では“onomatopée”とは言わないのです。このことは、英語の“onomatopoeia”でも同じです。英語の“onomatopoeia”は、「 擬態語」のことを含めません。
なぜなら、欧米の言葉には、「擬態語」それ自体が極めて少ないからです。
つまり欧米の言語には「 擬音語」は、ほんの少しだけ。ほとんど「 擬態語」は、見受けられないのです。
そのために、もともと欧米の言語には、「 擬態語」を指ししめす単語そのものがないのです。
まあ、考えてみればもっともです。だって、存在しないものに対しての単語は、ふつう用意されません。そしてこのことは、「 擬態語」についても当てはまります。「 擬態語」をあらわす単語が、欧米の言語では用意されていないのです。
そんなわけで、“仏:onomatopée”や“英:onomatopoeia”ということばは「 擬音語」だけを意味して、「 擬態語」のことは意味しないということになるのです。
 日本語では、カタカナで「オノマトペ」といったら「擬態語」も含める
日本語では、カタカナで「オノマトペ」といったら「擬態語」も含める
- そういったわけで。
欧米に「 擬態語」があるのかどうかは、かなりアヤシいのです。
しかし、日本語には「 擬態語」が、とても多くあります。そのためレトリックを研究している人たちは、「 擬態語」に対応する欧米語を見つけようとしたのでしょう。
結果として、日本のレトリック用語では。
ふつう“仏:onomatopée”とか“英:onomatopoeia”という単語によって、「 擬音語」だけでなく「 擬態語」のことを含めています。つまり、カタカナで「オノマトペ」と書いてあれば、そのなかには「 擬態語」も一緒に入っていると考えられます。
なお。
このあたりについて、これ以上の細かいことは。『日本語解釈活用事典』(渡辺富美雄・村石昭三・加部佐助[共編著]/ぎょうせい)などを参照してください。
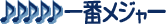
- 声喩・オノマトペ
 『擬音語・擬態語の読本』(尚学図書[編]/小学館)
『擬音語・擬態語の読本』(尚学図書[編]/小学館)
- この本は編著です。本にあるタイトルのように「擬音語」「擬態語」について、色々な人が解説しています。
 『犬は「びよ」と鳴いていた—日本語は擬音語・擬態語が面白い—(光文社新書 056)』(山口仲美/光文社)
『犬は「びよ」と鳴いていた—日本語は擬音語・擬態語が面白い—(光文社新書 056)』(山口仲美/光文社)
- 山口仲美氏は、日本での「オノマトペ」研究の第一人者。なので、広がりのある解説になっています。『表現と文体』(中村明ほか[共編]/明治書院)の第7章も、あわせてご覧ください。
 『実践 小説の作法(生活人新書 028)』(佐藤洋二郎/日本放送出版協会)
『実践 小説の作法(生活人新書 028)』(佐藤洋二郎/日本放送出版協会)
- この本は、小説を書くうえでの注意やアドバイスが載っている本です。この本の執筆者である佐藤洋二郎氏自身が、小説家です。
 『レトリック—日本人の表現—』(寿岳章子/共文社)
『レトリック—日本人の表現—』(寿岳章子/共文社)
- 漫画の擬声・擬態語]という節では、そのタイトル通り「漫画」における「擬声・擬態語」を扱っています。「漫画」での「声喩・オノマトペ」を扱っているこのページでは、もちろん参考になっています。
 『オノマトペ 擬音・擬態語をたのしむ 〈もっと知りたい! 日本語〉』(田守育啓/岩波書店)
『オノマトペ 擬音・擬態語をたのしむ 〈もっと知りたい! 日本語〉』(田守育啓/岩波書店)
- こちらも、「漫画」におけるオノマトペを扱っています。
 「ぴぴるぴる(略)♪」の正体は?
「ぴぴるぴる(略)♪」の正体は?
- これより下では。「ぴぴるぴる(略)♪」についての、ムダな考察。
いったい「ぴぴるぴる(略)♪」は、どんなカテゴリのことばなのか。「擬音」と書かれているのにもかかわらず、「 擬音語」ではないとすれば。「ぴぴるぴる(略)♪」のポジジョンというのは、どこらへんにあるのか。
結論として。個人的には、これは「 擬態語」だと考えています。
 「ぴぴるぴる(略)♪」そのように考える理由
「ぴぴるぴる(略)♪」そのように考える理由
- では。なぜ「
擬態語」だと考えるのか。
それは、「ぴ」という音に、思いつきで考え出したのではないと感じさせる要素があるからです。つまり、この「ぴぴるぴる(略)♪」というヤツ。これが、「言語の恣意性」という原則に、そむいている気がするのです。
長くなりそうなので、要点だけ書いておくことにすると。「ぴぴるぴる(略)♪」というフレーズにふくまれている「び」の音は、といったあたりの「 擬態語」にある「ピ」の音と、つながりがあるような気がしてならないのです。- 「ピシッとする」
- 「ピンピンする」
- 「ピリッとする」
だって。「ぴぴるぴる(略)♪」と言うと、撲殺したバラバラ死体が、もとどおりに復元するのだから。なにかこう、「元気な」「チカラがある」イメージが重なるのです。
以上、かなり乱暴な説明になってしまいましたが。「ぴぴるぴる(略)♪」=「 擬態語」、ということにします。
 「擬態語」は新しいことばをつくる
「擬態語」は新しいことばをつくる
- いままで書いてきた「ぴぴるぴる(略)♪」ということば。これは、まぎれもなく「新語」です。つまり、いままでにはなかったことばで、新しくつくりあげられたことばということです。
そういった、「新語」のつくりかた。これは、「 新造語法」というカテゴリにまとめられています。
くわしくは、「 新造語法」のページを読んでいただきたいのですが。かんたんにいえば、ということです。- 「 擬態語」などの「声喩・オノマトペ」は、新語をつくりだすチカラを強くもっている
こういったことも。「ぴぴるぴる(略)♪」が「 擬態語」だという考えかたをサポートするモノではないかと思います。
 「ぴぴるぴる(略)♪」の性質を考察した人は、ほかにもいる!
「ぴぴるぴる(略)♪」の性質を考察した人は、ほかにもいる!
- 「ぴぴるぴる(略)♪」の性質。こんな、どうでもいいことを考えた先哲が、ほかにもいました。
それは。- 「KPS 慶應サイコロジー・ソサエティー」
- にある、『「魔法の擬音」考』(Persona Vol.13第3号)。
こちらでも、「擬態語」という結論を得ているようです。けれども、ビミョーに考えの進めかたは異なっています。
でもまあ。とても親近感が、わいてきます。