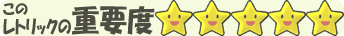サイト全部のトップ
サイト全部のトップ提喩 ていゆ synecdoche

- ゲンドウ「もういちど初号機を
- 起動させる」
- オペレータ「そんなっ! 無理です
- パイロットがいません」
- リツコ「レイにはもう……」
- ゲンドウ「問題ない
- たった今
- 予備が届いた」
提喩は、…どのように定義したらいいのか難しいレトリックの1つです。とりあえず、いちばん一般的な説明のしかたとして、
- A.「全体をあらわすことばのかわりに、その一部分を示すことばを使う」ばあい
- B.「その一部分を示すことばのかわりに、全体をあらわすことばを使う」ばあい
 「言葉の経済性」にとって、重要な役割を果たす
「言葉の経済性」にとって、重要な役割を果たす
- 「あの赤いの取って」という。たいていの場面では、それで事が足りる。それは、トマトかもしれないし、サンタクロースの衣装かもしれない。でも「サンタクロースの衣装」なんて正しい言い方を毎回していたら、疲れる。なので、「赤いの」で会話の相手が分かってくれそうなばあいには、そのようにいったほうが、「言葉の経済性」に合っているといえます。
 :簡便、有用、有益、経済的、便益、便利、利便、重宝、手抜き、省ける、はしょる、略する、省略、省力、ものぐさ、不精
:簡便、有用、有益、経済的、便益、便利、利便、重宝、手抜き、省ける、はしょる、略する、省略、省力、ものぐさ、不精
 全く同じ単語が、何度も出てこないようにする
全く同じ単語が、何度も出てこないようにする
- 日本語では、そうでもないのですが。とくにヨーロッパ圏では、同じ単語やフレーズが何度も現れるのを嫌います。そんなときには、「提喩」が役立ちます。もちろん日本語でも、同じように役立ちます。
 :見目よい、美し、綺麗、さっぱり、粹、通、芸がない、無芸
:見目よい、美し、綺麗、さっぱり、粹、通、芸がない、無芸
 受け手の想像力をかきたてる
受け手の想像力をかきたてる
- 受け手(読み手・聞き手)には、語らないことによって、想像力をかき立てられることのなります。
 :想像力、察する、イマジネーション、連想、趣き、情趣、風致、趣向、風韻、持ち味、ほのめかす、におわせる、示唆、黙示、ぼかす、ぼやかす、余情性、迂言、婉曲、遠回し
:想像力、察する、イマジネーション、連想、趣き、情趣、風致、趣向、風韻、持ち味、ほのめかす、におわせる、示唆、黙示、ぼかす、ぼやかす、余情性、迂言、婉曲、遠回し
 伝えたいと思っている言葉をイメージする
伝えたいと思っている言葉をイメージする
- まずは「提喩なし」で表現したばあい、どんな単語になるかイメージする。ここでは「美人」という単語をイメージした、とします。
 イメージした単語の「提喩」を見つけ、それを表現する
イメージした単語の「提喩」を見つけ、それを表現する
- つぎに、イメージした単語と「類または種」の関係にある(つまり「提喩」の関係にある)単語を見つけます。ここでは、「小野小町」にします。「小野小町」は「美人」の代名詞です。そして、「小野小町」は美人の一種となります。したがって、「提喩」だといえます。
なお、「小野小町」は「美人」の一部ではありません。したがって「換喩」の関係ではありません。
- 引用は『新世紀エヴァンゲリオン』1巻。
とても有名なので、ここまでのストーリーとか状況の説明はいらないかもしれない。だけど、かんたんに書いておきます。
で。主人公は、碇シンジ。
ある日シンジは、葛城ミサトという女の人から呼び出しを受ける。そして、ミサトに連れられ、ワケの分からないまま特務機関「ネルフ」へとやってきた。
じつは、この特務機関「ネルフ」というのは、シンジの父親である碇ゲンドウが勤めているところ。そして、父ゲンドウと息子シンジとのお互いの仲は、最悪だった。
そういった感じがバリバリ伝わってくるのが、引用のシーンです。
久しぶりにあったのだから、ふつうは「シンジ、元気だったか?」くらいのセリフがあってもいいはず。だけど、そんなセリフは一言もなく、ただ、「予備が来た」と。
つまり。
息子であるシンジのことを、「シンジ」と名前で声をかけない。ならば、緊急事態だし「(エヴァの)パイロット」という呼びかたをすると思えば、そうでもない。なんと、「(エヴァのパイロットの)予備」と言われる始末です。
ですが。
「提喩」について考えるときに注目するのは、まさにこの点です。ポイントは、ここにあります。つまり、- 「全体をあらわすことば」
- = シンジというエヴァのパイロット
- 「その一部分を示すことば」
- = 予備であること
ふつうなら「全体をあらわすことば」を使うはずのところを、わざわざ「その一部分を示すことば」(予備)を使うことにしている。そういったという理屈が成りたっています。ですので、この表現は「提喩」ということになるわけです。
 「提喩」の一般的な定義
「提喩」の一般的な定義
- 提喩をどのように定義するかについては、いろいろな説があげられています。そこで、このページでは、そのよな定義があるのかを見ていくことにします。
まず、いちばん一般的な説。それは、このサイトの最初【定義】に書いたものです。
国語辞典とかのレベルであれば、この「いちばん一般的な説」についてだけ説明が載っていればOKだといえます。
どうでもいいけど。
『新明解国語辞典』には、「提喩」の項目がない。「隠喩」とか「換喩」とかは、ちゃんとあるのに。しかも、「引喩」のようなマイナーそうなレトリック用語までちゃんと載せているのに。どうして「提喩」が見あたらないのだろう。
「提喩」はイラナイ、って考えなのかもしれない。そういう考えかたもあったりするので、この「提喩」をどうやって定義するかは本当に難しい。
 「種と類」「類と種」という関係にまとめる説
「種と類」「類と種」という関係にまとめる説
- 「提喩」とは、類と種の関係にもとづくレトリックをいうとする考えかたです。
レトリック学者のあいだでは。わりと多くの人が、この説を「いま現在での平均的な考えかた」としていたりします。
それは、決して「私も賛成」という意味ではありません。あくまで「議論のたたき台」として、これまではこのように考えられていたという意味で、この説が紹介されることは、よく目にとまります。
で、このような考えかたをとったばあい。
「提喩」というものは、という2つに分けられることになります。- 「類の提喩」
=—類によって、種をあらわす言いかた - 「種の提喩」
=種によって、類をあらわす言いかた
具体例を入れながら、もういちど確認しておくと、つぎのようになります。類でもって種をあらわす言いかた。- 「類の提喩」 :
- 類概念で、個物をしめすこと。
- 「類の提喩」
- (=特殊化の提喩)
- ・「花見」の「花」で、「桜」のことを言う
- ・「酒」で、「日本酒」のことを言う など
- 「種の提喩」 :
- 個物で、類概念をしめすこと。
- 種でもって類をあらわす言いかた。[[li](=一般化の提喩)
- ・「ご飯」で、「ソバ」や「スパゲッティ」のことを言う
- ・「人はパンのみにて生くるにあらず」では、「パン」で「食べ物全般」を言う など
「提喩」というのは、「カテゴリー間のでの言葉の置きかえ」「カテゴリー・レベルを変えること」だということになります。
というのは、
- 上位のカテゴリー(類)を、
- 下位のカテゴリー(種)で表したりするばあい
- →「類の提喩」
- 下位のカテゴリー(種)を、
- 上位のカテゴリー(類)に置きかえたりするばあい
- →「種の提喩」
いいかえれば。
「提喩」には、「一般化する働き」と「特殊化する働き」があるといえます。そして、一般化のほうは「くくること」であり、特殊化のほうは「例をあげること」にあたるといえます。
 「あるいは」と「かつ」という関係で「換喩」と区別する説
「あるいは」と「かつ」という関係で「換喩」と区別する説
- 古代から現代にいたるまで、「提喩とは何ぞや?」という問題はずっと考えられ続けてきました。ですが現在では、ここで書くことになる説が、いちばん有力だと思います。
その説というのは、「あるいは」と「かつ」という関係のどちらが成りたつかを考える説です。つまり、例えられることになったものと、実際使われた言葉との間に、とすることによって「提喩」と「換喩」とを区別して、「提喩」をハッキリさせようとする考えかたです。- 「かつ」という関係があれば、「提喩」
- 「あるいは」という関係があれば、「 換喩」
そういうことかというと、だいたい次のようなことになります。なおこの説では、「提喩」に似たレトリックといえる「 換喩」と比べながら「提喩」についての定義をします。ですので、あわせて「 換喩」についても書くことになります。
 「提喩」とは?
「提喩」とは?
- まず「提喩」。
例えば「木」ということばを使うことによって、「桜」だとか「梅」だとかをあらわしているばあいを考えてみましょう。
すると、木 = 桜「または」梅「または」竹「または」…といった関係になっていることが分かります。つまり、接続詞「あるいは」によって結ぶことのできる関係だということが言えます。
こういった接続詞「あるいは」によって結ぶことのできる関係を、「論理的和」の関係と考えることにします。そして、この「論理的和」つまり「あるいは関係」が成りたっているものについて、これを「提喩」と捉えることとします。
 「換喩」とは?
「換喩」とは?
- これに対して「
換喩」。
例えば「木」ということばを使うことによって、「枝」だとか「葉」だとかをあらわしているばあいを考えてみましょう。
すると、木 = 枝「および」葉「および」幹「および」根「および」…といった関係になっていることが読みとれます。つまり、接続詞「および」よって結ぶことのできる関係だということができます。
こういった接続詞「および」によって結ぶことのできる関係を、「論理的積」の関係とすることにします。そして、この「論理的積」つまり「および関係」が見受けられるものについて、これを「 換喩」とすることとします。
で。
このような考えかたは、記号によって説明や表現されることの多いものです。ですので、そのような記号についても触れておくことにします。
 「提喩」とは?——再び
「提喩」とは?——再び
- 上に書いたように、「提喩」とは「論理的和」です。でもって、総和の記号は「シグマΣ」です。なので、このような説では「シグマΣ」によって「提喩」を説明することがあります。
つまり、提喩Σ : 木=桜or梅or竹or……の公式で表せるもの。これが「提喩」といえます。
なお、このときには。「あるいは」という接続詞のかわりに、「or」という英語を使ったりします。
 「換喩」とは?——再び
「換喩」とは?——再び
- これに対して、「
換喩」のばあいは「論理的積」です。でもって、総積の記号は「パイΠ」です。まあ、数学をあまり知らない私(サイト作成者)には縁もゆかりもないのですが、とにかく「大文字パイ」というヤツは「総積」をあらわす記号です。なので、こちらは「パイΠ」によって「換喩」を説明することになります。
つまり、換喩Π : 木=枝and葉and幹and根……という式が成立するものです。これが「 換喩」となります。
なお、このときには。「かつ」という接続詞のかわりに、「and」という英語を使ったりします。
 この説に関する本
この説に関する本
- この説は、佐藤信夫先生の唱えていた考えかたを紹介するものです。つまり、根っこの部分では、グループμの『一般修辞学』にもとづく。その上で、佐藤先生による手直しを加えた。それが、この説です。
日本では現在、わりとこの定義が一般です。
なお。この説については。
いちばんの参考文献としてはやっぱり、佐藤先生の『レトリック感覚』をあげておきます。『一般修辞学』(グループμ[著]、佐々木健一・樋口桂子[共訳]/大修館書店)については、翻訳書なのでイキナリ飛びつくのはハードルが高いと思います。
 「提喩」に当てはまる条件を並べる説
「提喩」に当てはまる条件を並べる説
- ここを読んだいるあなた、えらい。こんなにも、つい読み飛ばしそうなところまで念入りに目を入れているなんて、書いている人として感動です。だってもう、パソコンをタイピングしている本人が、あきてきて疲れがたまっているんだから、しょうがない。
その上というか。これから書く 説は、かなりムダ知識です。なにせ、現代では使う人がほとんどいないのだから。
説は、かなりムダ知識です。なにせ、現代では使う人がほとんどいないのだから。
でも。サイトの都合上、ちょこっとは触れておかなければイケナイ説だと思うので、記していくことにします。
 この説の特徴——とにかく条件をいくつも並べる
この説の特徴——とにかく条件をいくつも並べる
- この説の特徴。それは、「提喩」に当てはまることになる条件をいくつも並べることになるということです。つまり、いくつか並んでいる条件のうちで、どれかに当てはまったら「提喩」といえるとする説です。
例えば。『レトリック感覚』では、4つの条件を並べているデュマルセの説明を要約して載せてあります。ですので、この4つを書き写して引用しておきます。
なお。いうまでもなく私(サイト作成者)はフランス語を読み書きできません。なので、デュマルセの本を読めるはずもありません。結果としてこれから書く「条件」というのは、『レトリック感覚』からの孫引きです。
条件——。- 《類による提喩》
——小さい集合をあらわすために、大きな集合(類)の名をもちいる表現 - 《種による提喩》
——大きい集合をあらわすために、小さな集合(種)の名をもちいる表現 - 《数の提喩》
——複数形をもちいる代わりに、単数表現を使う(またはその逆) - 《全体のかわりに部分を、また部分のかわりに全体をもちいる提喩》
- 《類による提喩》
 古くからある説
古くからある説
- この説は、古くからの伝統ある説です。年代物のレトリック書とかをヒモとけば、おそらくこの説で「提喩」のことを説明しようとしているはずです。近代のレトリックでは、ごくふつうの解説パターンでした。
でもまあ、こんにちでは人気がありません。というのは、条件がシンプルでないのです。とにかく、「提喩」に当てはまるような条件を、いくつもいくつも並べて、それに適合すれば「提喩」ですという説明のしかたなのです。
少ない人は、「提喩」となるばあいとして3〜4個くらいの条件を出します。ですが、多い人だと8個以上の条件を並べちゃいます。でもって、「この並んでいる条件の中で、どれかに当てはまれば「提喩」です」というふうに説明する。それってやっぱり、スマートではないです。
そんなわけで。
現在のレトリック学者のなかで、これを前向きに推しすすめる人はいないと思います。
じゃあ、どうしてこんなことを説明する本があるのか。それは、歴史的な流れを確認するためです。つまり、新しい説というのはどうしても、古い説のもっている弱い点や不完全なところを批判してできあがっていくものです。なので、流れとしてやはり古い説を書かざるをえなくなるのです。
まあ、ようするに。
知識としては、持っていたほうがいいかもしれない。でも、この【4.】説にやたらくわしくなる必要もなさそうです。
 参考文献
参考文献
- むかしの人の書いた本は、この説を説明するために場所をとっています。ですが、そういったもののうち、ほとんどが翻訳本です。なので、イキナリ読むのは難しいかなという感じがします。
現代の書物でいえば。『レトリック辞典』(野内良三/国書刊行会) あたりが、現在と比べたりしながら平均的に書いてあります。まあ、『辞典』という本の性質から、そうせざるをえなかったという面はあると思うけれども。
 「〜の一部」と「〜の一種」という関係で「換喩」と区別する説
「〜の一部」と「〜の一種」という関係で「換喩」と区別する説
- この説は、「提喩」と「 換喩」との区別が楽ちんです。どうしてかというと、「ただ公式に当てはめればいい」からです。
 「提喩」のばあい
「提喩」のばあい
- 「提喩」とは、「××は○○の一種である」という言いかたができるときに、この××と○○との関係のことを指します。
たとえば。
【桜は花「の一種」である】という言いかたができます。しかしながら、【桜は花「の一部」である】という言いかたはできません。このようなときに、この表現を「提喩」と呼ぶことにします。
 「換喩」のばあい
「換喩」のばあい
- これに対して「
換喩」とは、「××は○○の一部である」という言いかたができるときが、この××と○○との関係のことを呼びます。
たとえば。
【枝は木「の一部」である】という言いかたができます。けれども、【枝は木「の一種」である】という言いかたはできません。こんなばあいに、この表現を「換喩」とすることとします。
 参考文献
参考文献
- これは、瀬戸賢一氏が強く主張している考えかたです。なので、『日本語のレトリック—文章表現の技法—(岩波ジュニア新書 418)』(瀬戸賢一/岩波書店)が入門としては最適です。
あとは、『認識のレトリック』(瀬戸賢一/海鳴社)あたりに丁寧な説明があります。
 「提喩」を深く知る
「提喩」を深く知る
- …と。ここからは、中級レベルの人に向けた内容となっております。つまり、いろんな学者の「あーでもないこーでもない」論争を、ひとめぐりしてみたいと考えます。
それは、べつに。
急に「難しい」文章になるというわけではありません。私(サイト作成者)の持っている「できるだけ伝わりやすい日本語で書く」というモットーは、これっぽっちも動くことはありません。
ただ。
いままで上に書いたものだけで、「提喩」という「レトリック」が何であるかハッキリ分かった、という人はいないと思います。ですので、次にいくつかの説明の方法をかきとめて、この「提喩」に少しだけ迫っていきたいと思います。
 「一般化の提喩」と「個別化の提喩」
「一般化の提喩」と「個別化の提喩」
- いわく。「提喩」というレトリックは、さらに2つに分けることができるとされています。それは、「一般化の提喩」と「個別化の提喩」という2つです。
何がちがうのか。このページの一番さいしょに書いた、「提喩についてのとりあえずの説明」に沿っていえば。
「一般化の提喩」とは、A.「全体をあらわすことばのかわりに、その一部分を示すことばを使う」ばあいのことです。わざわざ「そういうもの一般をあらわすことば」を使うので、「一般化の提喩」と呼びます。
逆に、「個別化の提喩」とは、B.「その一部分を示すことばのかわりに、全体をあらわすことばを使う」ばあいのことです。この「個別化の提喩」は、「特殊化の提喩」ともいいます。わざわざ「そのなかでの個別例・特殊例をあらわすことば」をもちいるので、「個別化の提喩」とか「特殊化の提喩」とかいう名前がついています。
さいしょに書いた「人はパンのみにて生くるにあらず」という例文は、【A.「全体をあらわすことばのかわりに、その一部分を示すことばを使う」ばあい】ということになります。ですので、【B.「その一部分を示すことばのかわりに、全体をあらわすことばを使う」ばあい】に当てはまる例文をあげてみることにします。
みなさんご存じのように日本人は春になると、公園などで宴会を開いたりするのですが、これを、「花見に行く」といいます。でもよく考えると、ちょっとヘンです。だって、ぜったいに「ツバキ」とか「タンポポ」とかを見に行くわけがないのだから。つまり、ここでいう「花」というのは「サクラ」に決まっているのです。なのに、「サクラ」とは言わずに「花」と表現する。
では。なぜこれが、「個別化の提喩」となるのか。それは、次のような条件にあてはまるからです。それはつまり、という理論が当てはまるからです。ですので、これは「個別化の提喩」となるわけです。- 「全体をあらわすことば」 = 花<
- 「その一部分を示すことば」 = サクラ
わざわざ「全体をあらわすことば」(サクラ)を使うことにしている
 ジミな「提喩」
ジミな「提喩」
- この「提喩」は、とても地味なレトリックです。普段の会話などで使われても「レトリック」だと気がつかないくらい、非常に地味です。
それはつまり、なかなか「これぞ提喩だ」という表現には出くわさないということもできます。
しかし、地味だということは。
見かたを変えれば、人が物事を見たり聞いたり判断したりするときの「基本」だということもできます。つまり、世の中のことを自分のものとして受け入れようとするときには、いつでも「提喩」の機能が動き働いているということができます。
「提喩」はその地味であるがゆえに、日常の生活ではよく使われ、重要な役割を果たしています。
 「提喩」と他のレトリックとの関係
「提喩」と他のレトリックとの関係
 「提喩」の基本的性質
「提喩」の基本的性質
- この「提喩」は、とても地味なレトリックです。普段の会話などで使われても「レトリック」だと気がつかないくらい、非常に地味です。
それはつまり、なかなか「これぞ提喩だ」という表現には出くわさないということもできます。
しかし、地味だということは。
見かたを変えれば、人が物事を見たり聞いたり判断したりするときの「基本」だということもできます。つまり、世の中のことを自分のものとして受け入れようとするときには、いつでも「提喩」の機能が動き働いているということができます。
「提喩」はその地味であるがゆえに、日常の生活ではよく使われ、重要な役割を果たしています。
 「提喩」—「換喩」—「隠喩」という3つの関係
「提喩」—「換喩」—「隠喩」という3つの関係
- さて。
この「提喩」—「換喩」—「隠喩」というものを、どのようにバランスをとって位置づけるか。そのことは、そのまま「提喩とは何か」ということにつながります。つまり、「提喩」についての定義をどのようにするかということと、深く密接に関係するわけです。
なので、ここには突き詰めたことは書きません。
ですので。
いろいろと、説や考え方が分かれているのですが。ここには、かるく「箇条書き」で書いておくにとどめます。とまあ。かるく「箇条書き」とかいいながら、長くなってしまいました。でも、これでもサワリ程度なんです。ことば足らずなところ、理論不足なところが目につきます。でも、このくらいの説明にとどめておきます。- 1. 「提喩」と「換喩」との区別をあきらめる立場
- →
- 「提喩」と「換喩」とを、キッチリ分けることは不可能。
- なので、これを1つにまとめようとする考えかた。
- このように考えると、「提喩」と「換喩」とは同じグループで、
- 「隠喩」は別のグループということになる。
- 2. 「隠喩」を「二重の提喩」とする立場
- →
- 1回だけのカテゴリー変換を「提喩」として、2回のカテゴリー変換を「隠喩」とする考えかた。
- このように考えると、「提喩」と「隠喩」とは同じグループで、
- 「換喩」は別のグループということになる。
- 3. 「換喩」を「隠喩」に含める立場
- →
- 「換喩」について「隠喩」と区別をつけないでおく考えかた。
じつはアリストテレスがはじめに「隠喩」という用語を使ったときの意味は、これにあたる。
このように考えると、「換喩」と「隠喩」とは同じグループで、「提喩」は別のグループということになる。
- 4.どうにかして、「隠喩」と「提喩」と「換喩」の3つを区別しようとする立場
- →
- 「隠喩」と「提喩」と「換喩」の3つは、
- それぞれ違ったものだとする考えた。
- これについての理屈づけは、いろいろある。
- けれど、とりあえずそういったことを目指している説はみんなここに入れることにする。
- ほとんどのレトリック学者は、
- 理想としてはこれがGOODだと思っているはず。
- このように考えると、「隠喩」も「提喩」も「換喩」も、
- それぞれ別のグループということになる。
 「提喩」と「換称」との関係
「提喩」と「換称」との関係
- 人間について「提喩」を当てはめたばあい。
そのときは、「 換称」というレトリックとも重なります。
どうしてかというと、「 換称」というのは、というレトリックだからです。つまり、「本当の名前」と「通称・あだ名」とのあいだに、「提喩」の関係があるというわけです。- 本当の名前のかわりに、通称・あだ名で呼ぶ
- 特定の人を呼ぶことばをつかって、通称・あだ名とする
このあたりについてくわしくは、「換称」の項目をご覧ください。
また。
この「提喩」が極端になって、もともとのイメージがなくなるほどになっているばあい。これを、「失形象法」として細分化することがあります。
 「提喩」と「季語」との関係
「提喩」と「季語」との関係
- 『日本の修辞学』(外山滋比古/みすず書房)では、「俳句の季語」は「提喩」の性質を持っているとしています。たとえば、「花は早北へ移りし京都かな 泊月」という俳句に使われている「花」という季語。これについて、次のように述べています。この花は、春もろもろのものが包含されている。ただの桜の花だけではない。—(略)—。そればかりではない。花という季語を用いることによって、古来、この季語を入れた有名無名の句をすべて背後に背負っている。としています。

- 提喩

- シネクドキ
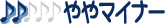
- 代喩
 『新修辞学—反〈哲学的〉考察—』(菅野盾樹/世織書房)
『新修辞学—反〈哲学的〉考察—』(菅野盾樹/世織書房)
- 「提喩」について、グループμに対抗する考え方を書いているものとして参考になります。
 『レトリック事典』(佐藤信夫[企画・構成]、佐々木健一[監修]、佐藤信夫・佐々木健一・松尾大[執筆]/大修館書店)
『レトリック事典』(佐藤信夫[企画・構成]、佐々木健一[監修]、佐藤信夫・佐々木健一・松尾大[執筆]/大修館書店)
- 「提喩」に関しては佐々木健一氏が執筆を担当しています。ですので、佐々木健一氏の考える「提喩」について、学ぶことができると思います。